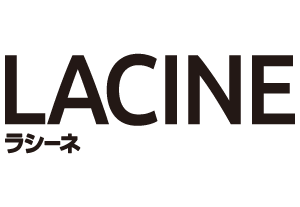犬の平均寿命と長生きの秘訣を解説!注意すべき病気&事故って?
 #犬の平均寿命
#長生き
#長寿のポイント
#犬の平均寿命
#長生き
#長寿のポイント
「犬の平均寿命って何歳?」という疑問は、犬を飼うにあたって気になる部分でしょう。
犬の寿命は人間よりも短く、飼い主さんが愛犬の最期を見届けることになります。
それでも、愛犬とは少しでも長く一緒に過ごしたいですよね。
そこで今回は、以下の内容について解説します。
・犬の平均寿命は何歳?
・犬の平均寿命が伸びている要因
・気を付けたい病気と事故
・犬に長生きしてもらう方法
犬の平均寿命に関する知識だけでなく、長生きの秘訣もご紹介します。
愛犬と少しでも長く暮らせるよう、必要な知識を身につけましょう。
1. 犬の平均寿命は何歳?小型犬・中型犬・大型犬ごとに解説
2019年度における犬の平均寿命は14.1歳です。
この平均寿命はアニコム ホールディングス株式会社が発行した「家庭どうぶつ白書2021」に掲載されています。
14.1歳という寿命は、鳥やうさぎと比べれば長い寿命ですが、人間と比べると短いですよね。
「家庭どうぶつ白書2021」では、犬種により平均寿命に差があることも明らかにされています。
「家庭どうぶつ白書2021」のデータを参考にし、小型犬・中型犬・大型犬ごとの平均寿命を解説します。
1-1. 小型犬の平均寿命
犬種の標準体重10㎏以下を小型犬として分類した場合、小型犬の平均寿命は14.4歳です。
小型犬・中型犬・大型犬の中で最も平均寿命が長いのは小型犬となっています。
犬種別の平均寿命ランキングでは、第一位がトイ・プードルで15.3歳、第二位がミニチュア・ダックスフンドとビション・フリーゼが同率で14.9歳となっており、小型犬の平均寿命を押し上げています。
1-2. 中型犬の平均寿命
犬種の標準体重10㎏以上20㎏未満を中型犬として分類した場合、中型犬の平均寿命は13.4歳です。
小型犬よりも平均寿命が短くなっていますが、犬種によりバラつきがあります。
中型犬で人気の高い柴犬の平均寿命は14.8歳、ビーグルは13.3歳、フレンチ・ブルドッグは11.2歳です。
1-3. 大型犬の平均寿命
犬種の標準体重20㎏以上を大型犬として分類した場合、大型犬の平均寿命は11.5歳です。
小型犬・中型犬・大型犬の中で最も平均寿命が短いのは大型犬となっています。
大型犬は体が大きい分、臓器にかかる負担も大きくなっており、平均寿命が短くなる傾向があるのではないかと言われています。
大型犬の成長スピードが小型犬より早いことも、寿命に関係していると考えられるでしょう。
2. 犬の平均寿命は伸びている!推移の要因5つ
「家庭どうぶつ白書2021」によると、犬の平均寿命は2019年度において14.1歳ですが、2009年度は13.1歳でした。
10年間で犬の平均寿命は1年伸びたことになり、今後も平均寿命は伸びていくと考えられます。
ギネス記録には、最高齢の犬として29歳5ヵ月まで生きたオーストラリアン・キャトル・ドッグのブルーイーが認定されています。
犬の平均寿命にはまだまだ伸びしろがありそうですね。
犬の平均寿命が伸びた理由5つを解説します。
2-1. 室内飼育の増加
犬の平均寿命が伸びた理由の1つは、室内飼育を選択する飼い主さんが増えたことです。
「いぬ・ねこのきもち WEB MAGAZINE」が調査した「犬猫との暮らし調査2021」では、回答した飼い主さんのうち86%が完全室内飼いを選択しているという調査結果が出ました。
室内飼育は屋外よりも交通事故や感染症のリスクが減るため、寿命が長くなると考えられます。
2-2. 犬を救う医療の進歩
日本の獣医学の進歩も、犬の平均寿命が伸びた要因です。
新しい手法や技術を取り入れ、病気の早期発見が可能になり、治療できる病気が増えました。
農林水産省の「飼育動物診療施設の開設届出状況(診療施設数)」によると、「小動物その他」の診療施設は2010年で10,350件、2020年で12,247件となっており、動物病院の数も増加しています。
近くに動物病院があれば、緊急時に助かる可能性も高くなるため、動物病院数の増加も犬の平均寿命が伸びた要因かもしれません。
2-3. 飼い主の健康意識
愛犬の些細な変化に気づいて、すぐに動物病院を受診する飼い主さんが増えています。
飼い主さんの健康意識も高まっているといえるでしょう。
結果的に病気の早期発見につながり、平均寿命を押し上げています。
飼い主さんの健康意識の高まりは、インターネットで簡単に情報収集できるようになったことが関係していると考えられます。
2-4. ドッグフードの品質向上

飼い主さんの健康意識が高まるにつれ、犬の健康に配慮したドッグフードが求められるようになりました。
各企業はニーズに応えるため、栄養管理士や獣医師を雇い、おいしくて健康的なドッグフードを日々開発しています。
日常的に与えるドッグフードだけでなく、病気を治療するための療法食も進化しており、食事だけで病気を治療できるケースもあります。
ドッグフードの品質向上は間違いなく犬の平均寿命を伸ばしているでしょう。
2-5. 避妊・去勢手術の普及
ほとんどの動物病院で避妊・去勢手術が推奨されており、避妊・去勢手術の普及率が上がっています。
避妊・去勢手術のメリットは「望まない妊娠を防ぐ」「マーキング行動をなくす」「性ストレスからの解放」「生殖器関連の病気予防」などです。
特に「生殖器関連の病気予防」は前立腺がんや乳がんなど、死因にもなる病気の発生率を抑えられるため、大きなメリットだといえます。
避妊・去勢手術の普及は、平均寿命が伸びた要因になっていると考えられるでしょう。
3. 犬が寿命を迎える要因は?死因となる3つの病気

現代の獣医学では治せない病気もあり、老衰ではなく病気で亡くなる犬も多いのが実情です。
犬がなりやすい病気について知り、予兆に気づけるようにしておきましょう。
犬の死因となる3つの病気を解説します。
3-1. 死因になりやすいのは悪性腫瘍
犬の病気による死因で最も多いのは悪性腫瘍、いわゆるがんです。
がんは、早期発見・早期治療が大切です。定期的に健康検診を受けましょう。
手術・放射線治療・抗がん剤などの治療方法があります。
皮膚のがんであれば体表の腫れやしこりでがんに気づける場合があるため、日常的にスキンシップを図りながら健康チェックをすることが大切です。
3-2. 初期症状の少ない心臓病
犬の病気による死因で2番目に多いのが心臓病で、心奇形・フィラリア症・心筋症・弁膜症などの種類があります。
特に多いのは僧帽弁閉鎖不全症です。
咳・呼吸困難・失神などの症状があらわれる頃にはすでに病気が進行しており、手術や投薬治療が必要になります。
心臓病は初期症状があまりなく、飼い主さんが早期発見するのは困難な病気です。
獣医師であれば心雑音の有無で判断できるため、早期発見できるよう定期的に健康診断を受けましょう。
3-3. 尿検査で早期発見できる腎臓病
犬の病気による死因で3番目に多いのは腎臓病で、急性腎臓病と慢性腎臓病があります。
急性腎臓病はぐったりする・嘔吐・おしっこが出ないなどの症状があらわれ、急激に状態が悪化する病気です。
対応が遅れると命を落とす危険もありますが、早急に治療すれば回復できる可能性があります。
慢性腎臓病は最初に多飲多尿の症状があらわれますが、この時点ですでに腎機能が4分の1に低下していると言われています。
慢性の場合は腎機能を回復させられないため、病気の進行を抑えるための治療が必要です。
慢性腎臓病は目に見える初期症状がありませんが、定期的に尿検査をうければ早期発見ができます。
4. 犬の寿命を守る!家庭で気を付けたい3つの事故

犬の老化は防げませんが、予防することで防げる事故は多くあります。
愛犬の寿命を事故で縮めないために、事故を防ぐ方法を知っておきましょう。
家庭で気を付けたい3つの事故を解説します。
4-1. 異物の誤飲による閉塞
家庭で起こりやすい事故は、異物の誤飲です。
犬は興味の引かれるものを見つけると、口の中に入れて遊ぶことがあるため、誤って飲み込む危険があります。
消しゴム・アクセサリー・人間用の薬など、小さいものを床の上に放置しないようにしましょう。
誤飲は窒息や胃や腸の閉塞などにつながり、命を落としたり手術が必要になったりすることもある重大な事故です。
4-2. 拾い食いから生じる中毒症状
人間の食べ物の中には、犬にとって有害な物があります。
飼い主さんが与えていなかったとしても、犬が勝手に拾い食いをして中毒症状を起こすこともあるでしょう。
特に注意が必要なのは、タマネギやニンニクなどのネギ類・チョコレート・タバコです。
中毒症状で死に至ることもあるため、犬が有害な物を口にしないよう、届かない場所にしまっておきましょう。
4-3. 命の危険もある熱中症
熱中症は人間だけでなく、犬にとっても危険な事故です。
散歩中だけでなく、室内でも熱中症のリスクがあり、死に至ることもあります。
「エアコンで室温を調整する」「日陰の場所をつくる」「いつでも水分補給できるようにする」などの対策をしましょう。
特に7~8月が要注意です。また、湿度の高い6月も要注意です。
5. 犬の寿命を伸ばしたい!長生きしてもらう5つの方法

犬は家族の一員であり、できるだけ長生きしてほしいと思うのが飼い主さんの心情でしょう。
いつかは寿命が訪れてしまいますが、長生きしてもらうために飼い主さんにできることもあります。
犬に長生きしてもらう5つの方法を解説します。
5-1. ワクチン接種で病気を予防する
ワクチン接種は感染症の予防に非常に効果的なため、適切な時期に動物病院で接種しましょう。
主に推奨されているのは「狂犬病ワクチン」「混合ワクチン」「フィラリアの予防薬」「ノミやダニの予防薬」の4種類です。
狂犬病ワクチンは生後90日以上の犬は接種するよう、狂犬病予防法で義務付けられているため、必ず接種しなければなりません。毎年1回の接種をします。
混合ワクチンは生後2~3ヵ月頃から3回にわたって接種し、フィラリア・ノミ・ダニの予防薬は春から投薬してもらいましょう。
その後、混合ワクチンは1年に1回の接種をします。
5-2. 定期的に健康診断を受診する
目に見える初期症状がほとんどない病気もあるため、定期的に健康診断を受診しましょう。
1歳から年1~2回の頻度で健康診断を受けるのが理想です。
獣医師による診察・身体検査・血液検査・尿検査・便検査などが主な内容ですが、健康診断の内容は動物病院により異なります。
さらに詳しく検査したい場合は、人間ドックのペットバージョンである「ペットドック」を受けましょう。
ペットドックではレントゲン検査や心電図などの検査が受けられます。
5-3. 健康的な食生活を意識する
愛犬に長生きしてもらうには、健康的な食生活を意識する必要があります。
愛犬の年齢や体質に合ったドッグフードを選び、適量を与えましょう。
肥満になると糖尿病や心血管疾患などの病気になるリスクが高まります。
総合栄養食を主食として適量を与え、おやつを与えすぎないことが大切です。
また、ドッグフードのなかには、コストカットのために低品質な材料を使っている商品もあるため、原材料に注意して選びましょう。
5-4. 適度な運動を心がける
愛犬の健康を維持するために、適度な運動を心がけましょう。
適度な運動はストレスの発散になり、からだだけでなく心の健康にも役立ちます。
1日1~2回を目安に散歩へ連れていきましょう。
室内で遊べるおもちゃも用意しておくのがおすすめです。
シニア犬は激しい運動が負担になることもあるため、健康状態に合わせて運動量を調整することが大切です。
5-5. 愛犬の些細な変化を見逃さない
犬は言葉を話せないため、体調の不調には飼い主さんが気づいてあげる必要があります。
食欲・排泄物の様子・歩き方など、些細な変化を見逃さないようにしましょう。
日頃から愛犬の様子をよく観察し、スキンシップを図ることが大切です。
毛並みや皮膚の状態もチェックしましょう。
愛犬の体調がすぐれないときは動物病院を受診し、対処してもらう必要があります。
6. まとめ
2019年度の犬の平均寿命は14.1歳ですが、将来的にはさらに寿命が伸びていくと考えられます。
飼い主さんはワクチン接種・健康診断・日々の食事など、愛犬の健康を気遣う行動を心がけましょう。
愛犬に健康的な食事を提供したい飼い主さんには、「獣医師監修のドッグフード|ビューティープロ」がおすすめです。
最新の栄養学に基づいたレシピを採用し、年齢・体型・体調に合わせたラインアップを展開しています。
「ビューティープロ」の詳細についてはこちらを参考にしてください。
おすすめのドッグフードはこちら

「ビューティープロ ドッグ」シリーズ
●優れた栄養バランスで免疫力を維持。
●コラーゲン3000mg/kg配合。
●食べやすいハート型粒。
●着色料無添加。
●獣医師監修。
●総合栄養食。
TOPへ