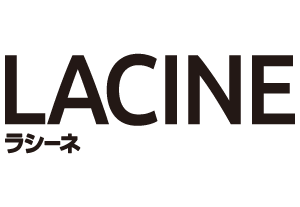猫飼育に必要な避妊・去勢手術を完全解説|メリット・費用・手術の流れ
 #避妊
#去勢
#避妊・去勢手術
#避妊
#去勢
#避妊・去勢手術
最近では、飼い主の責任として猫の避妊・去勢手術をするよう推奨されています。
これから猫の飼育をはじめようと考えている方も、避妊・去勢手術をした方がいいという意見を耳にしたことがあるのではないでしょうか?
一方で、以下の疑問をお持ちの方もいるのではないかと思います。
「室内飼育でも、避妊・去勢手術は必要?」
「避妊・去勢手術は、いつ頃にどのような流れで受ければいいの?」
「手術には、どのくらいの費用がかかるの?」
そこで、猫の避妊・去勢手術に関して疑問に思われる点をすべて解決すべく、知っておきたい情報をまとめました。
飼い主としての責任をしっかりと果たしつつ、健康的かつおだやかに愛猫と過ごしていきたいと思っている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
1.猫を飼育するうえで避妊・去勢手術をする目的・メリット
そもそも、なぜ避妊・去勢手術が推奨されているのでしょうか?
愛猫が子猫を産めない体になってしまうのがかわいそうだと感じていませんか?
しかし、猫の避妊・去勢は飼い主のエゴではなく、愛猫にとってもとても意義・メリットのあることです。
まずは、避妊・去勢手術をおこなう目的・メリットについて明確にしておきましょう。
1-1. 予期しない妊娠を避ける
避妊・去勢手術の最大の目的は、予期しない妊娠を避けることです。
メス猫は、生後6~12ヵ月の頃に妊娠可能な身体になり、一度の妊娠で4~8頭の子猫を産みます。
年間の出産回数は2~4回程度で、1年に生まれる子猫の数は約20頭です。
さらには、生まれた子猫たちもすぐに出産できるようになるため、放置しておくと猫の数は爆発的に増えます。
猫が増えすぎて飼い主さんの手に負えなくなり野良猫化してしまう問題は、大きな社会問題の一つです。
飼い主さんが面倒を見切れなくなった子猫は、運が良ければ保護猫として里親を見つけられるかもしれませんが、保健所で殺傷処分を受ける可能性もあります。
また、誰かに飼って欲しくて路上などに猫を放す方もいるかもしれません。
このような行為は「遺棄」とみなされ、違法行為にあたります。100万円以下の罰金が課せられるため、倫理的にも法律的にも許されない行動です。
日本の現状としては、全体の8割ほどの飼い主さんが、愛猫の避妊・去勢手術をしています。

1-2. 問題行動を防ぐ
避妊・去勢手術をしていない猫は、問題行動を起こしやすくなることも知られています。
問題行動が、より顕著に見られるのはオス猫です。
発情期になると、オス猫は満たされない性的欲求による強いストレスを感じて、徘徊・マーキング・夜鳴きなどの行動をとりがちです。
これらの問題行動により、飼育が困難になるだけでなく、近隣の住民とのトラブルに発展してしまうこともあります。
避妊・去勢手術をすることで、問題行動の予防になると同時に、愛猫のストレス軽減の効果も期待できます。
1-3. 病気の予防につながる
避妊・去勢手術は、病気の予防にも効果があります。
<メスの場合>
- 乳腺腫瘍・・・乳腺腫瘍は、発情期のホルモンバランスの変化によって発症することが多く、避妊手術により発症リスクをかなり低減させられることが分かっています。猫の乳腺腫瘍の大半は悪性で、死に至る可能性のある重い病気です。
- 子宮の病気・・・避妊手術の際に子宮を摘出するため、子宮の病気(子宮蓄膿症など)にかからなくなります。
- 性感染症の回避・・・ほかの猫との交尾による猫エイズなどの感染症対策になります。
<オスの場合>
- 乳腺腫瘍・・・・乳腺腫瘍は、稀にオスも発症する病気です。去勢手術によって、発症リスクをかなり下げられます。
- ケンカや交通事故の予防・・・発情期にメスを求めて徘徊していると、外でほかの猫とケンカをしたり、交通事故にあったりする可能性があります。
- 性感染症の回避・・・(メスと同様)
上記のように避妊・去勢手術は、オス猫にもメス猫にもかなり効果的です。
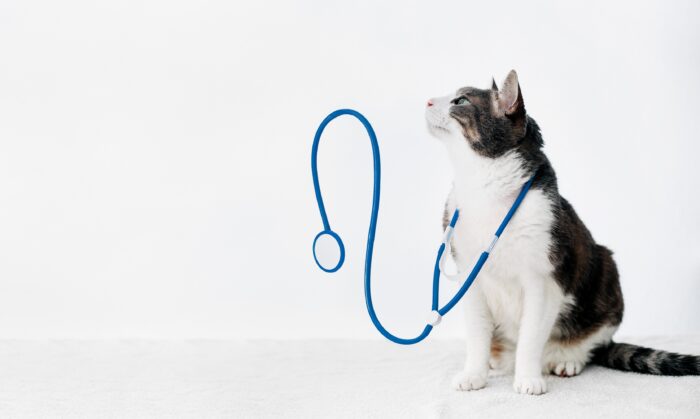
2.飼育時に猫の避妊・去勢手術をするデメリット
猫の避妊・去勢手術のメリットを紹介しましたが、反対にデメリットはないでしょうか?
デメリットについて意識をすることで、避妊・去勢手術を受ける際の注意点にもつながります。
この章では、避妊・去勢手術の2つのデメリットを解説します。
2-1. 費用がかかる
避妊・去勢手術には、15,000~30,000円の費用がかかります。
また、上記の手術費用の他に麻酔・入院・術後の薬代などの費用がかかります。
※例えば、血液検査費用の相場は4,000~10,500円、入院料は2,000~5,000円です。
具体的にどれだけの費用が掛かるかについては、個々の動物病院の価格設定によって異なります。
したがって、かかりつけの動物病院でどれほどの費用がかかるのかについてチェックしておきましょう。
2-2. 太りやすくなる傾向がある
避妊・去勢手術をすると、太りやすくなる傾向があります。
その理由は、避妊・去勢手術によってホルモンバランスが崩れるためです。
対策をすれば、初回の発情がくる時期(なるべく若い時期)に避妊・去勢手術を受けることで肥満のリスクは減ります。
飼い猫が肥満になると、糖尿病リスクの上昇をはじめとした健康リスクにつながります。
対策は、2点です。
- 適度に運動をすること
- 栄養バランスの優れた高タンパクなキャットフードを与えること
これらを意識することで肥満の予防に加えて、健康維持にも大きな効果が期待できます。
ビューティープロでは避妊・去勢手術後の飼い猫に向けのラインナップを取り揃えておりますので、是非ご確認ください。

ビューティープロ キャット 避妊・去勢後用
●子猫から使える避妊・去勢後用。
●おいしさそのまま必要なたんぱく質量は維持し、脂肪分約20%カット※。
(※ビューティープロ キャット 成猫用比)
●着色料無添加、食べやすいハート型粒。
●獣医師監修。

3.飼育猫の避妊・去勢手術の流れ
動物病院にて避妊・去勢手術を受ける際には、どのような流れで手術をおこなうのでしょうか?
一般的に、避妊・去勢手術はかかりつけの動物病院にておこないます。
基本的な流れを把握することで、スケジュール感の把握や不安の解消につながると思いますので、目安として参考にしていただけたら幸いです。
3-1. 生後6ヵ月~手術可能
飼育猫の避妊・去勢手術ができるのは、生後6ヵ月ごろからです。
ただし、手術可能な時期は獣医師の考え方や子猫の発育状況によっても異なる可能性があります。
時期的に早すぎると、手術によるリスクが大きいため、手術を受ける予定の動物病院に相談して疑問や不安を解消しましょう。
避妊・去勢手術は、予約制になっています。
手術のタイミングは、基本的に獣医師がおすすめするタイミングに従えばOKです。
ただし、上述のとおり、猫は4ヵ月頃から妊娠可能な身体になるため、できるだけ早めに手術を受けた方が安心です。
3-2. 事前検診
事前(手術がおこなわれる数日前頃~当日)に、手術を受ける動物病院にて事前検診を受けます。
検診をおこなう目的は、手術前に健康状態の異常がないかをチェックするためです。
主な検査項目は以下のとおりです(検査項目は動物病院によって異なります)。
- 血液検査・・・赤血球と白血球の数や臓器の働きに異常が生じていないかをチェック。
- ウイルス検査
- レントゲン検査
また、ワクチンの有効期限が過ぎているケースでは、手術の14日前頃までにワクチン接種が必要です。
これらの事前検査は、基本的には1日で実施されます。
3-3. 手術前日
手術に向けて、前日から準備をおこないます。
特に注意をしたいのは、食事についてです。胃の中に食べ物が残っていると、手術中に逆流して喉につまってしまい、非常に危険です。
従って、手術の前日には食事や水分の摂取の制限をおこないます。
夜9時頃までに食事を終わらせ、朝食は与えないでください。
お水は朝まで与えてください。
獣医師の先生の指示に従いましょう。
3-4. 手術当日
愛猫の健康状態などに問題がなければ、予定通り手術がおこなわれます。
指定された時間に動物病院に来院して、愛猫の健康状態に問題がなければ愛猫を動物病院に預けて、飼い主さんは手術が終わるまでは自宅で待機することになります。
手術にかかる時間は、およそ1~2時間程度です。
全体麻酔をして、剃毛・消毒・外科手術の順でおこなわれます。
一般的には、麻酔が覚めて愛猫が目覚め、容体が安定したころに飼い主さんが迎えに行くことになります。
目安としてオス猫の去勢手術の場合は、朝預けて夕方お迎えに行く。メス猫の避妊手術の場合は、1~2日入院になります。
3-5. 抜糸(術後7~10日)
メス猫の場合は、避妊手術から7~10日ほど経過したタイミングで抜糸をおこないます。
抜糸までの間に、経過観察のために動物病院の受診が必要なケースもあります。
通院の頻度や必要性は、状況に応じてケースバイケースですが、普段と異なる様子が生じているときには要注意です。
チェックすべき状態は、次の点です。
- 便がいつもよりもゆるい
- 食欲がなく、元気がない
- よく鳴くなど、普段と異なった行動をしている
- 傷口をなめている
これらの症状が見られる場合や、どこか気になる点があるときには、様子を見ずにすぐに動物病院を受診しましょう。
また、術後の期間は、傷口が開かないように飼い主さんが注意をすることも必要です。
激しい運動をしないように特に注意しましょう。
抜糸の処置は比較的手軽にできるため、短時間で完了することが多いです。

3-6. 術後の肥満に注意
避妊・去勢手術直後は、肥満のリスクがあることを紹介しましたが、手術の直後は特に注意が必要です。
ホルモンバランスの変化により基礎代謝が下がってしまうにも関わらず、食欲が増すことが多く、体重が増加しがちです。
術後の容体が安定した後、運動不足にならないよう運動させることを意識していきましょう。
4.飼育猫の避妊・去勢手術には助成金が受けられる可能性あり
猫の避妊・去勢手術に対して、助成金を展開している自治体が数多くあります。
具体例をいくつか見てみましょう。
- 東京都世田谷区・・・区民の飼い猫の手術費用を一部補助。
・避妊・去勢手術(メス)に対して6,000円
・去勢手術(オス)に対して3,000円
- 愛知県名古屋市・・・市民の飼い猫に対して手術費用を一部補助。
・避妊・去勢手術(メス)に対して6,300円(名古屋市から2,100円、名古屋市獣医師会から4,200円)
・去勢手術(オス)に対して3,150円(名古屋市から1,050円、名古屋市獣医師会から2,100円)
- 京都府京都市・・・市民の飼い猫に対して手術費用を一部補助。
・猫の避妊・去勢手術に対して5,000円(京都市から2,500円、京都市獣医師会から2,500円)
※京都市の補助金は、犬・猫・オス・メス同額です。
補助金・助成金の有無は、市町村の考え方次第であるため、お住まいの自治体が補助金を出しているか否かをまずはチェックしてください。※補助金・助成金は、年度ごとに予算が組まれます。前年までは補助金があったのに急に出なくなってしまったり、年度の途中で募集が終了してしまったりするケースもあるため、常に最新の情報をチェックするようにしましょう。
5.まとめ
猫を飼育する際に、猫の飼育や避妊・去勢手術を受けることは今や飼い主さんにとってのマナー・責任の一つです。
避妊・去勢手術を受けることで、予期しない子猫の出産が避けられることはもちろんですが、猫の情緒安定や病気の予防などのメリットもあります。
手術のデメリットは、費用がかかることと太りやすくなることです。
かかりつけの動物病院でしっかり説明を受けましょう。
費用については、助成金を活用できるケースもあるため、お住まいの自治体の情報をぜひチェックしてください。
太りやすくなる問題については、フードの見直しや適度な運動の習慣を取り入れることで対策できます。
記事内では手術の大まかな流れについてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2209/full.pdf
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2209/full.pdf
https://petfood.or.jp/data/chart2020/5.pdf
http://kalkan.jp/catguide/article_12.html
https://cat.benesse.ne.jp/withcat/content/?id=13004
http://www.kayama-ah.jp/14997362995751"
TOPへ