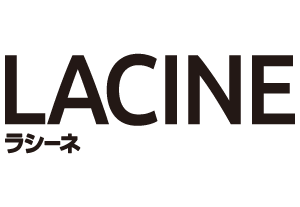愛猫が下痢をしたときの原因・対策とは?
 #猫の下痢
#猫の下痢対策
#猫の下痢の原因
#猫の下痢
#猫の下痢対策
#猫の下痢の原因
猫の下痢はよくみられる症状です。
しかし、下痢の症状の背景には深刻な病気や体調不良が潜んでいることもあります。
珍しくないことだからといって、まったく心配がないわけではありません。
愛猫の下痢を発見したときに、飼い主さんは適切な対処を迅速におこなう必要があります。
早期に対応することで重症化を抑えられるため、対応のスピードは非常に重要です。
では、猫が下痢をしたときにどのような対応をすればいいのでしょうか?
この記事では、愛猫が下痢をしたときの原因を解説したうえで、適切な対処法をご紹介します。
1、猫の下痢は危険?見分けるポイント
猫の下痢はそれほど珍しいことではありませんが、下痢のなかには危険を示している場合も!
その見極めのポイントを把握し、愛猫が下痢をしたときに冷静かつ迅速に対処できるようしましょう。
見極めはケースバイケースですが、病気や体調不良の可能性があるのは以下のいずれかに該当する場合です。
- 下痢の症状が何日間も継続している
- ごはんをあまり食べず、いつもと比べて元気がない
- 嘔吐などの他の症状を併発している
- 便の状態に異常が見られる(血が混じっている・粘性がある・水のようにシャバシャバしている)
また、上記に該当しない場合でも、飼い猫が子猫や高齢猫である場合は少しの体調不良が生命の危険につながる場合もあるため要注意です。
これらの危険な状況に該当する場合は、一刻も早く動物病院に診てもらいましょう。
2、猫の下痢の原因

猫の下痢の原因は複数考えられます。
専門の獣医師でなければ判断ができないケースもありますが、原因の種類を知れば飼い主さん自身も安心ですし、適切な対処を行えるようになるでしょう。
この章では、猫の下痢の原因として考えられるものをご紹介します。
2-1. ストレス
猫は、ストレスに対してとても敏感です。
特に注意が必要なのは、大きな環境変化が起こったとき。
例えば、引っ越しやペットが増えたときなどです。
ときには、飼い主さんにとっては些細だと考えられることに強いストレスを感じることもあります。
愛猫が急に下痢を繰り返すようになったら、環境の変化などのストレス要因がないか疑ってみましょう。
2-2. 食事
いつも食べているキャットフードが体質に合わないとき、下痢を起こす場合があります。
個々の相性もあるため、必ずしも評判の良いキャットフードなら問題ないわけではありません。
もし、キャットフードを切り替えたタイミングで愛猫が下痢を繰り返すようになったら、一度キャットフードとの相性を疑いましょう。
頻繁にキャットフードを変えたり複数のキャットフードをローテーションで与えたりしている場合、原因のフードがわかりにくいため基本的にキャットフードは1種類に絞った方がいいです。
また、新しいフードを切り替えるときにいきなり全量を新しいものに替えると、下痢をしてしまうことがあります。
フードが合っているかを見極めるためにも、おなかへの負担を減らすためにも2~3週間ほどかけて少しずつ新しいフードの割合を増やしていきましょう。
2-3. アレルギー
猫が発症しやすいアレルギーは、いくつかの種類があります。
・食物アレルギー
キャットフードに含まれる肉・卵・牛乳・穀物などの原材料に対してアレルギー反応を示すことがあります。これらのアレルゲンは、一般的なキャットフードに多く含まれているものです。食物アレルギーの症状はケースバイケースですが、下痢のほかに皮膚の赤み・身体のかゆみ・などの症状が現れやすいです。
・ハウスダスト・ダニ
ホコリやダニなどの細かな物質を空気と一緒に吸い込むと、アレルギー症状が起こる場合があります。ハウスダストやダニに対するアレルギーを完全に防ぐのは不可能ですが、部屋を定期的に掃除したりダニ対策グッズを用いたりすれば、ほこり・ダニの発生を抑えられます。
・ノミ
ノミは、猫にとって身近な動物ですが、アレルギーの原因となる存在でもあります。ノミ除けグッズなどを効果的に活用し、ノミの発生を最小限に抑えましょう。
2-4. 異物の誤飲
家庭内にある人間用の食べ物や屋外の残飯などを口にした結果、体調を崩すこともあります。
例えば、人間用のおやつは猫にとっては添加物やスパイスなどの刺激が強すぎることがあります。
残飯に関しては、食べ物が日持ちしなかったり、農薬・洗剤などの有害物質が含まれているかもしれません。
大切なのは、普段から飼い主さんが猫の行動範囲の安全を確認することです。
2-5. 病気・疾患
病気や疾患によって、内臓や身体の機能に不調が生じると下痢を起こすことがあります。
便の状態と健康状態は密接に関わっているため、下痢を招く病気や疾患は数多くあります。
3、猫が下痢をしているときに疑われる病気とその症状
下痢を招く病気を特定するには、専門家である獣医師の診断が必要です。
しかし、何の病気が原因で下痢を起こしているのか見当もつかなければ、診断が出るまで不安ですよね?
この章では、猫の病気を招く症状を4つご紹介します。
3-1. 感染症
猫の下痢を招く感染症として特に有名なものは、「猫伝染性腹膜炎」や「猫汎白血球減少症」です。それぞれ簡単に解説します。
・猫伝染性腹膜炎
猫コロナウィルスによる猫の感染症の一種です。
ウイルスによる症状自体はそれほど重症化するものではありませんが、変異によって猫伝染性腹膜炎を発症すると発熱・食欲不振・体重減少などの症状を招きます。
猫伝染性腹膜炎は、発症後1ヵ月程度で命を落とすなど、危険性の高い病気です。
現代ではまだ完治のための治療法が発見されておらず、症状を抑えるために免疫力をアップさせる対策がとられています。
・猫汎白血球減少症
パルボウイルスによる感染症です。猫汎白血球減少症の特徴は、便に血が混じることと嘔吐を繰り返すことです。
子猫が発症すると、重症化しやすいため要注意です。
特効薬はまだ開発されておらず、点滴や栄養補給などの注射による対処がおこなわれます。
また、発症前であればワクチンによる予防も可能です。
3-2. 寄生虫・細菌感染
猫に下痢を起こさせる寄生虫・細菌は,以下のとおりです。
- サルモネラ菌
- 大腸菌
- 線虫(回虫)
- トキソプラズマ
- コクシジウム
- ジアルジア
- トリコモナス
これらは、普段の生活の中で非常に身近です。
特に保護猫や外に出る猫は、外での生活や集団生活で感染のリスクが高くなっている可能性があります。
寄生虫がいても症状を示さないこともあるので、健康診断の際に便検査を受けてみてもいいかもしれません。
感染リスクを抑えるためには、普段の食事や飲用水の衛生状態に気を配りましょう。
3-3. 内臓疾患
内臓の疾患は、便の状態に直結します。
特に影響が生じやすいのは、腸・肝臓・胆のう・膵臓などです。
病気・疾患の内容によって症状が異なり、初期症状が強く出るものとそうでないものがあります。
3-4. 内分泌系の疾患
ホルモン異常などの内分泌系の疾患が下痢を引き起こすこともあります。
高齢の猫の甲状腺異常では、症状の判断や原因の特定が非常に難しく、動物病院においてもX線検査やエコー検査をしないと原因特定ができないケースが珍しくありません。
1年に1回は健康診断を受けるように心がけましょう。
4、猫が下痢をしたときの対処法

愛猫が下痢をしたときに飼い主さんに与えられる最も重要な役割は、適切な対処をすることです。
3つのポイントをご紹介します。
4-1. 動物病院を受診
愛猫の下痢が気になるとき、最も基本的な対応はできるだけ早く動物病院を受診することです。
便の色・回数・量など診療のヒントになります。
また、便を持参することや写真を撮っていくことも役立ちます。
できる限り独断での判断を避けて、専門家である獣医師に相談するようにしましょう。
少しでも不安を感じる場合、ためらったり迷ったりする必要はありません。
4-2. 水分を与える
猫が下痢を起こしているときには、体内の水分が失われます。
猫は、元々それほど水を飲みたがらない動物ではありますが、下痢を起こしている際には脱水症状を起こすリスクが高まります。
例えば、動物病院を受診するまでの間など、まずは水分を多めに与えることを意識してください。
このとき与える水は基本的に水道水で問題ありません。(ミネラルウォーターを与える場合は、軟水であれば概ね問題ありませんが、特に海外製の硬水の場合はマグネシウムやカルシウムの配合量が多くなるため避けましょう)
また、愛猫が水を飲みたがらないときには猫用の経口補液を使用したり、スポイトで口元に水分を垂らしたりするなどの対策も有効です。
また、水分を与えるのはあくまでも動物病院を受診するまでの応急処置です。
4-3. じっくり様子を見る
愛猫の様子を、いつも異常にていねいに観察することも重要です。
- 動物病院での獣医師からの質問に的確に答えるため
- 容態の変化にいち早く気がつくようにするため
また、症状が落ち着いた後も、観察を続けるよう意識してください。
下痢の再発やそのほかの病気が発症した際に、様子の違いを的確に説明できるようにするためです。
5、猫が下痢をしているときの食事のポイントとは?
猫が下痢をしているときに注意すべき点の一つが、食事です。
下痢が生じているときには健康の維持と栄養の摂取を同時に考える必要があります。
この章では、猫の健康のポイントを3つの観点からご紹介します。
5-1. 内臓に負担をかけないように注意
下痢をおこしているときには、内臓に負担をかけないように慎重に対処する必要があります。
強い負担がかかってしまうと、下痢が治りにくくなるばかりか症状が悪化してしまう危険性があります。
内臓(特に消化器系)に負担をかけないために必要な点は以下のとおりです。
・普段よりも食事量を少し減らす
胃腸の調子が悪いときにごはんをたくさん食べると、胃腸に負担がかかります。無理をして食べても、結局嘔吐や下痢で体外に排出されてしまうと栄養を摂取できません。したがって、飼い主さんがあえて分量を調整することで、栄養をきちんと吸収させられます。
ただし、食事量の調整によって必要な栄養素が十分に確保できない場合もあります。
全てをご自身で判断せずに、分量や与え方については動物病院の獣医師に相談してください。
・ドライフードはふやかしてから与える
固形のドライフードを水でふやかしてから与えれば、消化吸収しやすくなります。その結果、胃の負担が軽減され、下痢によって不足しがちな水分補給ができます。水でふやかしたものを愛猫が食べたがらない場合は、ぬるま湯でふやかしてもOKです。水よりも香りが立ちやすく、食欲がそそるでしょう。
ただし、ミルクなど水以外の水分でふやかす際には、一度獣医師に相談してから試してくださいね。
5-2. 絶食はNG
「絶食すれば猫の胃腸に負担がかからないのではないか」といった意見もありますが、下痢時の絶食は厳禁です。
ただでさえ、水分や栄養素が失われているときに絶食をすると、水分不足や栄養失調により健康状態が急激に悪化する危険性があります。
特に、元々の体力が低い子猫の場合は重大な症状に陥りやすいため絶対にご自身の判断で絶食させないでくださいね。
5-3. 子猫の場合は獣医師に相談
子猫の下痢に対しては、慎重に対応する必要があります。
子猫は下痢をしやすく、体調も急変しやすいため、飼い主さんにとっては非常に大変です。
ごはんの量を減らしたり、ミルクを与えたりなど愛猫のためを思って取った行動がかえって逆効果になる場合もありますから、必ず獣医師に相談しましょう。
もちろん飼い主さんが何か不安に感じるようなことがあれば、子猫に限らずどんなときでも専門家である獣医師を頼ってくださいね。
6、まとめ
猫は下痢をしやすい動物です。
頻繁に下痢をするからこそ、動物病院にかかるべきか様子を見るべきか迷うことも多いでしょう。
結論としては、少しでも迷いがあるときは動物病院の受診をオススメします。
何事もなければそれに超したことはありません。
また、費用の面も気になるかもしれませんが、もし病気だった場合に治療が遅れたときのリスクを考えれば、出来るだけ早めの受診が適切です。
TOPへ