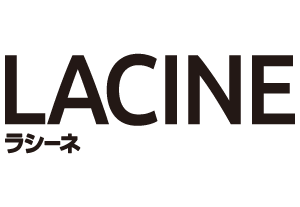猫は魚が好きじゃない?魚を食べるリスク5つ&主な栄養素5つ
 #魚
#猫に魚
#魚を食べる事のリスク
#魚
#猫に魚
#魚を食べる事のリスク
日本では「猫は魚が好き」というイメージが一般的ですよね。
猫が魚をくわえているイラストを目にすることも多いでしょう。
しかし、猫は魚よりも肉を好む肉食動物です。
「“猫は魚が好き”というイメージがついたのはなぜ?」
「猫が魚を食べるのはよくないの?」
「キャットフードは原材料に魚を含んでいる方が良い?」
このような疑問を抱くかもしれませんね。
そこで今回は「猫は魚が好き」と言われる理由をはじめ、猫が魚を食べる際のリスクや適切な与え方について解説します。
魚に含まれる栄養素の効能やキャットフードについてもご紹介しますよ。
愛猫に健康的な食事を与えたい飼い主さん必見です。
1. 「猫は魚好き」って本当?猫にとっての魚とは

日本では「猫は魚好き」というイメージが一般的ですが果たして本当なのでしょうか。
「猫は魚好き」というイメージが定着した理由も含めて「猫にとって魚はどのような位置づけの食材なのか」を解説します。
1-1. 猫は魚よりも肉を食べるのが好き
1977年に動物行動学者のボードローが行った実験によると、猫の好む食肉ランキングは1位から5位までヒツジ・ウシ・ウマ・ブタ・鳥と続き魚は6位です。
「猫は魚好き」というのは日本人の勝手な思い込みなのかもしれませんね。
そもそも猫は水に濡れるのが好きではないため、水の中を泳ぐ魚を狩ることはほとんどありません。
室内で猫を飼っている場合は体感しにくいかもしれませんが、猫は魚よりもネズミや鳥を狩る姿の方が自然です。
1-2. 「猫は魚好き」のイメージは日本だけ
庶民が猫を飼うようになったのは江戸時代で、人間が食べ残した米や魚などを猫のフードとして与えていたようです。
明治時代になり肉が食べられるようになりましたが、肉は高級な食材だったため食べ残しになることはほとんどありませんでした。
猫は食べ残しの中からなんとか動物性たんぱく質を摂取するために魚を食べていたのだと考えられます。
昔から日本では猫が魚に飛びつく姿が多く見られてきたため、「猫は魚好き」というイメージが定着したのでしょう。
猫が魚に飛びついていたのは「魚が好き」という理由ではなく「生きるため」だったのかもしれませんね。
とはいえ、猫は生後3ヵ月までに食べたものを好む傾向があるため、魚を原材料として含むフードの人気が高い日本では魚好きになる猫も多いでしょう。
1-3. 猫にとって魚は注意点の多い食べ物
魚には猫の健康に役立つ栄養素が多く含まれており猫にとって魅力的な食材ですが、生魚を食べて寄生虫に感染したり、骨で口を傷つけたりするリスクもあります。
猫にとって魚は注意点の多い食べ物でもあるため、飼い主さんは猫が魚を食べる際に生じるリスクを知っておくことが大切です。
2. 猫が魚を食べる際のリスク5つ
猫が魚を食べる際には適切な方法で与えなければ体調を崩すことがあります。
猫が魚を食べることで生じる代表的なリスクは「アニサキス寄生虫」「ヒスタミン食中毒」「黄色脂肪症」「チアミン欠乏症」「尿路結石」の5つです。
それぞれのリスクについて原因及び症状を解説します。
2-1. アニサキス寄生虫
アニサキス寄生虫はサバ・アジ・サンマなどの青魚の内臓に寄生しやすい線虫で、鮮度が落ちると内臓から筋肉へ移動します。
スーパーで販売されている魚でもアニサキス寄生虫が潜んでいることがあるため注意が必要です。
寄生された魚を生で食べるとアニサキス寄生虫が胃に入って食中毒を引き起こします。
食中毒になると嘔吐や激しい胃の痛みが生じるため、感染に気を付けたい寄生虫です。
温める程度では死滅しない寄生虫ですが、しっかりと加熱することで死滅するため焼いたり煮たりして与えましょう。
2-2. ヒスタミン食中毒
魚に含まれる「ヒスチジン」というアミノ酸は細菌によって分解されると「ヒスタミン」を生成します。
魚を常温で放置すると細菌が増殖するため「ヒスタミン」は新鮮でない生魚に生成されやすい物質です。
ヒスタミンを含む魚を食べると、ヒスタミン中毒を起こして下痢・嘔吐・顔や舌の腫れ・めまい・じんましんなどの症状が出ます。
ヒスタミンは熱に強い性質を持っており加熱しても分解されないため、魚を新鮮なうちに調理することが大切です。
2-3. 黄色脂肪症
黄色脂肪症とは不飽和脂肪酸を長い期間にわたって過剰摂取することで発症する病気です。
魚は不飽和脂肪酸を多く含む食材のため、猫に与える際は量に注意しなければなりません。
黄色脂肪症になると脂肪が酸化して黄色く変性し、炎症を起こしてしこりになります。
しこりには痛みが生じるため歩き方が不自然になったり、腹部を触られるのを嫌がったりすることが多いようです。
黄色脂肪症の症状が見られたらすぐに魚を与えるのを止め、動物病院を受診しましょう。
2-4. チアミン欠乏症
チアミン欠乏症はチアミンが欠乏することによって発症する病気でビタミンB1欠乏症とも呼ばれます。
生魚や甲殻類に含まれている「チアミナーゼ」という酵素はチアミンを破壊するため、魚を過剰摂取するとチアミン欠乏症を発症することがあります。
チアミン欠乏症を発症すると「歩き方がおかしくなる」「徘徊する」などの神経症状がみられやがて死に至ります。
早期に治療されれば治る病気のため重症化する前に動物病院を受診しましょう。
魚に含まれる「チアミナーゼ」は加熱によって効果を失う酵素なので加熱することで予防できます。
2-5. 尿路結石
尿路結石とは膀胱や尿道に結石が溜まることで血尿や排尿困難などの症状が出る病気です。
尿のpHがアルカリ性に傾くと「ストルバイト結石」、酸性に傾くと「シュウ酸カルシウム結石」ができ、猫の尿路結石で最も多いのは「ストルバイト結石」です。
ミネラルの影響で尿のpHが傾くため、ミネラルの過剰摂取は尿路結石を引き起こすリスクがあります。
魚はカリウム・カルシウム・マグネシウムなどのミネラルを豊富に含む食材なので、与えすぎないように注意しなければなりません。
尿路閉塞の症状を放置すると腎臓病を引き起こすリスクもあるため発症した場合は動物病院を受診しましょう。
尿路結石の予防法として魚の摂取量に気をつける他、新鮮な水を常に飲める環境を整えることが大切です。
水分摂取量が少ないと尿が濃くなり尿路結石のリスクが高まります。
3. 猫に魚を与える際の適切な方法4つ
猫に魚を与えることは寄生虫への感染や過剰摂取による病気の発症などのリスクがありますが、適切な与え方をすることでリスクを回避できます。
魚には猫の健康に役立つ栄養素が豊富に含まれているため、リスクを回避すればメリットの多い食材です。
猫に魚を与える際の適切な方法4つを解説します。
3-1. 骨を取り除いてから与える
魚の骨が刺さると猫の口・喉・胃腸を傷つけてしまう危険があるため、骨を取り除いてから与えることが大切です。
「よだれを垂らしている」「口を閉じない」などの症状が見られた場合は魚の骨が刺さっているかもしれません。
骨が刺さった状態で食事すると骨がさらに深く刺さってしまう可能性があるため、刺さった場合は食事を中断して動物病院を受診しましょう。
3-2. 加熱処理する
生魚を猫に与えると寄生虫への感染やチアミン欠乏症を引き起こすリスクがあるため、加熱処理してリスクを回避しましょう。
生身が残らないようにしっかりと火を通すことが大切です。
また猫は熱い食べ物が苦手なため加熱後は冷ましてから与えましょう。
3-3. アレルギー反応に注意する
愛猫に魚を初めて与える際には食物アレルギーを持っている可能性を考えて、様子を見ながら少量ずつ与えましょう。
数日食べているうちに症状が出ることが多いため長い目で様子を見ることが大切です。
嘔吐や下痢などの消化器症状や皮膚トラブルが現れたらアレルギー反応を起こしている可能性があります。
症状が出たら動物病院を受診し、アレルギーの原因が魚であると判明した場合、今後は魚を与えないようにしましょう。
3-4. 愛猫の適量を守る
猫に魚を与えすぎると肥満だけでなく、黄色脂肪症・チアミン欠乏症・尿路結石などの病気を引き起こすリスクもあるため、適量を守ることが大切です。
主食は魚ではなく総合栄養食のキャットフードにし、魚はかつお節をトッピングで与える程度にしておくと良いでしょう。
缶詰など市販のキャットフードであればパッケージに適量が記載されていますよ。
4. 猫の健康に役立つ魚に含まれる主な栄養素5つ

魚には豊富な栄養素が含まれており、適切な方法で与えれば猫の健康に役立つ食材です。
魚に含まれる主な栄養素5つの概要と効能を解説します。
4-1. アミノ酸バランスに優れた「たんぱく質」
魚に含まれる動物性たんぱく質は体の組織を作る他、エネルギー源となるなど重要な役割を持つ栄養素です。
肉類と同じくらい必須アミノ酸の含有バランスが良いため、愛猫が肉アレルギーの場合は魚で動物性たんぱく質を摂取させると良いでしょう。
4-2. 不飽和脂肪酸の「DHA」と「EPA」
不飽和脂肪酸は過剰摂取すると黄色脂肪症の原因になりますが、不飽和脂肪酸は猫にとって必要な栄養素でもあります。
不飽和脂肪酸であるDHAは脳のはたらきをサポートし、EPAは血中に血栓ができるのを防ぎます。
DHAとEPAを適量摂取すれば高齢対策への効果が期待できるでしょう。
4-3. 骨や歯を健康に保つ「カルシウム」
カルシウムは骨や歯を健康に保つ重要な栄養素で筋肉を動かす働きがある他、神経の伝達にも関係しています。
まさに猫が生きていくために欠かせない栄養素ですが、過剰摂取すると尿路結石の原因になるため注意が必要です。
4-4. 猫に必須のアミノ酸である「タウリン」
タウリンは猫にとって必須のアミノ酸で、体内で合成できないため食事で摂取する必要があります。
心臓や目の健康を保つ他、動脈硬化を予防し肝機能を強化する栄養素です。
5. 猫に魚を食べさせたい!キャットフードの原材料は?
猫に魚を与える際には「骨を取り除く」「加熱する」などの処理をしなければならず手間がかかります。
愛猫に安全かつ簡単に魚のもつ栄養素を摂取させたい場合は、魚を原材料に含むキャットフードを選択するのがおすすめです。
キャットフードの原材料としてよく使われる「魚の加工品」を4種類に分けて解説します。
5-1. 猫用のかつお節
人間用のかつお節・まぐろ節は塩分が多すぎるため、キャットフードに含まれる猫用のものは塩分少なめで製造されています。
キャットフードに含まれている場合がある他、猫用のおやつとしてかつお節のみでも販売されていますよ。

5-2. 乾燥した小魚・チップ
乾燥させた小魚やちりめんなど魚の姿が残っているものと、鮭チップやかつおチップなど魚を加工して製造されたものがあります。
総合栄養食のキャットフードに含まれる場合はドライ粒とは別にトッピングとして含まれているのが一般的です。

参照:「COMBO公式サイト コンボ キャット ドライ | 日本ペットフード」
5-3. フィッシュパウダー
フィッシュパウダーとは魚を砕いて粉状にしたものを指しフィッシュミールとも呼ばれます。
魚の頭部やヒレなどの不要部位を原料とするのが一般的ですが魚全体を原料とするものもあります。

5-4. フィッシュエキス
フィッシュエキスとは魚を茹でたときに出た煮出し汁のことで、キャットフードのパッケージには「フィッシュエキス」と表示されるため、どのような魚を使用しているのか分からない場合がほとんどです。
煮出し汁から油だけを分離したものはフィッシュオイルあるいは魚油と呼ばれます。

6. まとめ
今回は猫の健康に役立つ魚の栄養素や適切な与え方などを解説しました。
適切な与え方をすれば魚の栄養素は猫の健康に役立ちますが、寄生虫への感染・ヒスタミン食中毒・過剰摂取を原因とする病気などには注意しなければなりません。
とはいえ、骨を取り除く・加熱する・適量を量るなど、適切な与え方をするのはかなり手間がかかりますよね。
簡単に魚の栄養素を猫に摂取させたい場合は、原材料に魚を含んだキャットフードを主食にするのがおすすめです。
キャットフードであれば寄生虫への感染やヒスタミン食中毒を起こしたりすることもありません。
おいしさと健康にこだわったキャットフード「COMBO(コンボ)」は原材料に魚を含んでおり、愛猫の食事に魚の栄養素を取り入れたい方にぴったりのドッグフードです。
原材料や栄養価に注目してキャットフードを選択し、より健康的な食生活を目指しましょう。
「COMBO(コンボ)」の詳細についてはこちらを参考にしてください。
おすすめのキャットフードはこちら

「コンボ キャット」シリーズ
●1日分の栄養素がバランスよく摂れる。
●厳選素材をそのままに。
●豊富なトッピング。
●新鮮小分け。
●総合栄養食。
TOPへ